プログラミング教育が小学校で導入されたことにより、プログラミング的思考が注目されているのをご存じですか?聞き慣れない言葉に感じる方も多いかもしれませんが、子どもに人気の積み木遊びには、実はプログラミング的思考を育む要素がいっぱい。そこで今回は、知っておきたいプログラミング的思考についてと、プログラミング的思考を育む積み木遊びアイデアをご紹介します。
そもそもプログラミング的思考ってなに?

プログラミング的思考とは、「目的を達成するために必要な手順を順番に組み立てていく力」のことをいいます。難しく聞こえますが、何かを行おうとしたときに、どのような手順で、どのような順番で、どのように進めていくか、といった物事の順序に筋道を立てて考える能力がプログラミング的思考です。このプログラミング的思考は、2016年に文部科学省によって奨励され、小学校でプログラミング教育の導入が始まったことで、認知が広がりつつあります。AI技術の発展やITの進化、SNSの普及など、さまざまな情報であふれている現代において、何が正しい情報なのかを取捨選択する力や、問題解決の方法を自分で考える力は、将来必ず必要になるといわれています。
日常生活で育めるプログラミング的思考
プログラミング的思考とは、目的を達成するために必要な手順を順番に考えて組み立てていくこと。コンピュータに指示を出すプログラミングで考えると難しく感じますが、日常生活でプログラミング的思考を育む機会はたくさんあります。
たとえば、ブロックを使って「高いタワーを作りたい!」と思ったとき、子どもは無意識に「まず大きなブロックを下に、その上に中くらい、最後に小さいの」と順番を考えています。これがまさにプログラミング的思考なのです。「どうすれば思った通りにできるか」を考えることこそが、プログラミング的思考に直結していきます。
このように、日常生活のなかで子どものプログラミング的思考を育んでいるシーンはたくさんあります。親子で料理をすることなども、献立決めから食材決め、買い出し、調理工程、盛り付けと、目的達成のために順序ごとに行動することはプログラミング的思考の学びになっています。
積み木とプログラミング的思考の関係
遊びのなかでプログラミング的思考を育てるなら、積み木遊びは絶好の遊びといえます。
積み木遊びで思考力を伸ばすプロセスを見てみましょう。

子どもはただ遊んでいるだけでも、遊びを通して自然と「考える力」が育まれていくのが積み木遊び。プログラミング的思考に必要とされる、「順序・分岐・くり返し」を自然と行って遊びに結び付けることができるため、問題解決のための手順を考えたり、課題点を見つけて改善したりする力を自然と育むことができます。
おうちでできる積み木遊びアイデア

積み木は、遊び方に決まったルールがあるわけではありません。親子で「今日はこうやってみよう」と工夫して遊ぶだけで、プログラミング的思考につながる学びが自然と生まれます。以下では、おうちで気軽にできる積み木遊びのアイデアをご紹介します。
同じ形・色でルール化して並べてみる
「同じ形だけ並べよう」「同じ色だけ使ってみよう」など、積み木遊びのなかにルールを設けて遊びます。ちょっとした条件をつけることで、考える力が身につきますよ。
親子で「設計図」を作って考えてみる
簡単なものから壮大なスケールのものまで、あらかじめ作りたいものをイメージして、親子で設計図を作ってから積み木遊びに挑戦する方法もおすすめです。遊びでも真剣に、どうやったら作りたいイメージのものが正確に作れるか、使う積み木や数、順序を考えるきっかけになります。
同じ形を繰り返して積む
四角→三角→四角→三角というように、同じ形を繰り返し積む遊びもおすすめです。ただ並べるだけでも、同じものを使用してできるパターンを考える力を養うことができます。
どうして崩れたのかを一緒に考える
積み木遊びは崩れることも遊びの一貫です。大事なのは、積み木が崩れてしまった原因を一緒に考えてあげること。親子で失敗について話すことも学びのひとつです。トライアンドエラーの積み重ねは、プログラミング的思考につながる学びといえるでしょう。
積み木を選ぶときのポイント
いろいろな種類の積み木があるなかで、プログラミング的思考を伸ばす積み木にはいくつか特徴があります。一概にはいえませんが、積み木を選ぶ際の参考にしてみてはいかがでしょうか。
1.シンプルで応用が効く形
プログラミング的思考を伸ばすなら、シンプルで応用が効く積み木がおすすめです。組み合わせやすいシンプルな積み木は、発想が広がりやすく、また同じ形を使って複数のパターンも考えやすくなります。
2.ある程度形がそろっていると便利
形がバラバラで同じ形の積み木が少ないものよりも、同じ形の積み木が複数あり揃っている積み木のほうが、ルール遊びに使いやすいです。また、同じパターンを繰り返し作って遊ぶのにも便利です。
3.安全性
繰り返し遊ぶ積み木は、子どもにとって安全であることが前提です。手に触れて遊ぶものだからこそ、怪我や誤飲の心配がない積み木かどうか、万が一舐めたりしてしまっても安全かどうか、といった点には特に注意したいところです。国内産の積み木でアレルギーの少ない無塗装仕上げで、おもちゃの安全基準である「STマーク」認証がついた積み木なら安心です。
プログラミング的思考を育む「KIKKA」の積み木
設計から製造まですべて日本で行われている積み木「KIKKA」は、プログラミング的思考を育むのにぴったりな積み木です。KIKKAの積み木は12ピースで、特徴的な「X型」「K型」の2種類の積み木で構成されています。この特徴的な形状により、ただ縦に積むだけでなく、横に積んだり斜めに回転させたりして遊ぶことが可能です。2種類の積み木から生まれる積み木作品は、お子さまの創造性によって無限です。
また、積み木のサイズは一般的な積み木のサイズである4cm基尺で、小さなお子さまも手に持ちやすい大きさなので、積み木デビューにもおすすめです。国産材の最高級品である奈良の桧「吉野桧」を使用した積み木で、おもちゃの安全基準である「STマーク」も取得済。ひのきの風合いを最大限に活かした無塗装の積み木となるため、うっかりお子さまが舐めてしまっても安心です。箱を開けるたびに広がるひのきの香りは、リラックス効果があるだけでなく、抗菌・防臭・防虫効果など、ひのき特有のうれしい効果もたくさんあっておすすめです。
■KIKKA Japanese Wooden Toy /【国産】【ひのき・奈良】
「考える力」と「感じる力」を育む 知育積み木「KIKKA -キッカ-」

商品ページはこちらから
まとめ
小学校から始まるプログラミング教育に伴い、認知が広がるプログラミング的思考。多様化するこれからの社会にとって、幼児期のうちから身につけておきたい能力のひとつといわれています。プログラミング的思考は、日常生活を送るうえで料理や洗濯、買い物など、気づかないうちに自然と実行されているものですが、子どもに教えるうえでは積み木遊びがぴったりです。積み木は「手で考える」体験を通じて、プログラミング的思考を育てることができます。幼児期から自然に遊びの中で取り入れることができるため、親子で一緒に試行錯誤する時間が未来の学びにつながるのではないでしょうか。ぜひ参考にしてみてくださいね。
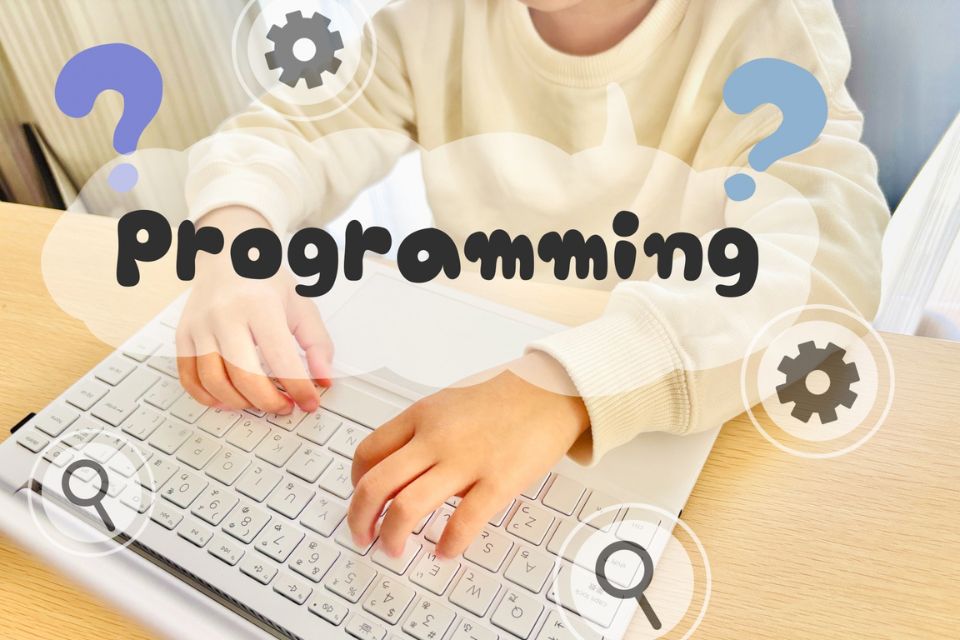





プログラミング的思考を伸ばすのにぴったりな積み木ってどんな積み木?